その6はこちら!
のりにぃ音楽理論 その6 コードの成り立ちとダイアトニックコード
ダイアトニックコードの復習
前回はダイアトニックコードというのは
どういうものなのかということを解説しました。
簡単にまとめると
- 1つの曲の中で基本的に出てくるコードは7つだけ
- それらのコードはメジャーかマイナーかが決まっている
- 何番目のコードがどんなコードになるかを知っておけばキーが変わっても対応できる!
ということでした。
今回は、それぞれのダイアトニックコードが
曲の中でどんな役割を持っているかを見て行きましょう!
これが分かると
コードブックをパッと見た時に
あ、これは始まりだな
これは場面が変わって盛り上がりだな
なるほど、これで曲が終わるんだな
ということが理屈で分かるようになりますよ!
1.トニックコード
まず、前回の表をもう一度見てみましょう。
例のごとくキーはCメジャーで考えます。
「何番目」という順番で考えるときは
スケールディグリーと言ったりしますが
ここではそのままⅠ~Ⅶと書きます。
ダイアトニックコード一覧
| ドミソ | レファラ | ミソシ | ファラド | ソシレ | ラドミ | シレファ | |
| Cメジャー | C | Dm | Em | F | G | Am | Bm♭5 |
| Ⅰ~Ⅶ | Ⅰ | Ⅱm | Ⅲm | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵm | Ⅶm♭5 |
まず、イメージとして
この曲で一番使用頻度の高いコードはどれだと思いますか?
それはもちろん(?)
ドレミファソラシドというくらいですから
Cがルートになっている「Cメジャー」です!
Ⅰのコードですね。
ドミソ~って鳴っていると
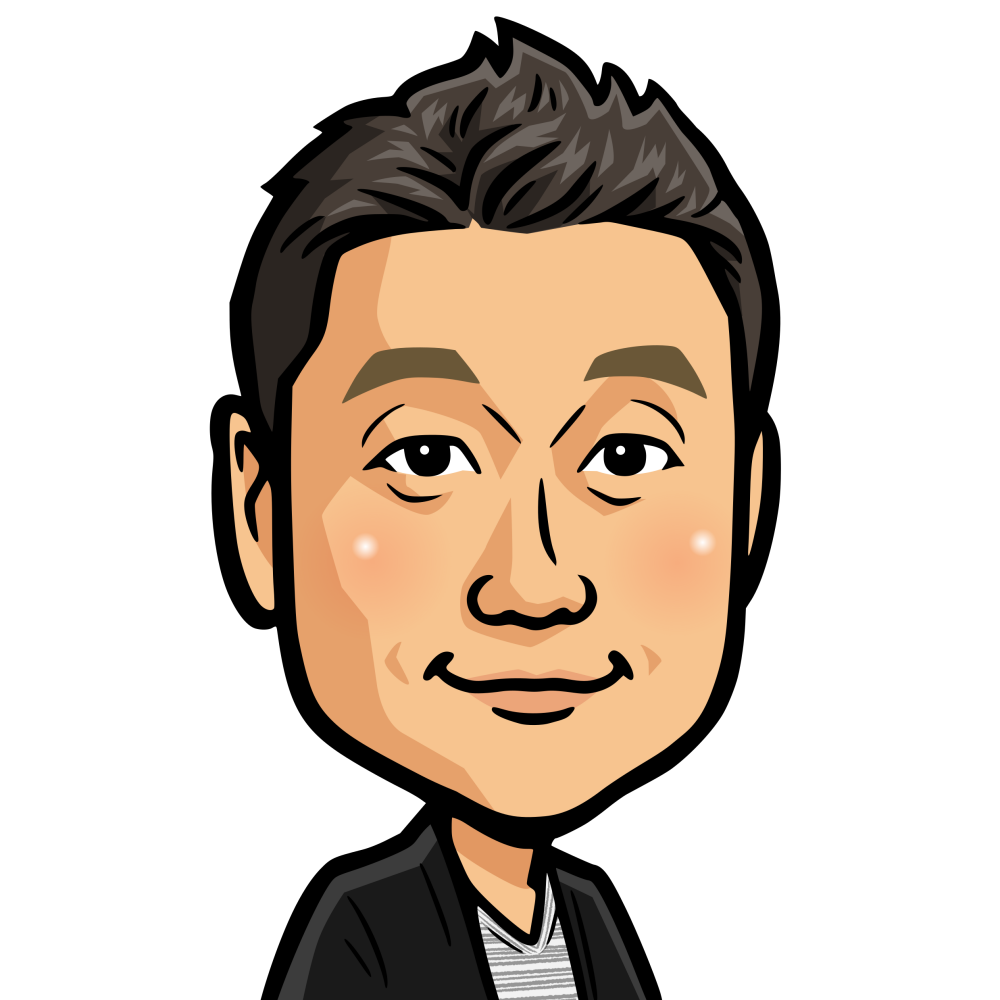
平和~、いつも通り~
って感じがしませんか?
これが、やはり基準になります。
このコードが鳴っていると、とても「落ち着き」ますね。
落ち着く音=主音ということで
このⅠ(今回はCメジャー)のコードのことを
トニックコードと呼びます。
例えてみれば、トニックコードは「自宅」のようなものです。
いつでも帰って来れる場所、自分の居場所、ホッとする場所
そんなイメージを持っていただければOKです。
2.ドミナントコード
では、次に重要なコードはどれでしょうか。
以前、導音の話をしたことを覚えていますか?
ルートの半音下からルートに戻るとホッとする…みたいなやつです。
Cメジャーの場合、ルートの半音下の導音はシ(B)です。
ということは、コードにおいてもシの音を弾いてやれば

早くドの音(トニック)に戻ってほしい!
という、聞き手の気持ちを引き出すことができます。
ド(トニック)で安定 ⇔ シで不安定
この安定と不安定を行ったり来たりして
曲は成り立っているのです。
では、シの音を鳴らすためには
どんなコードを弾けばいいでしょうか?
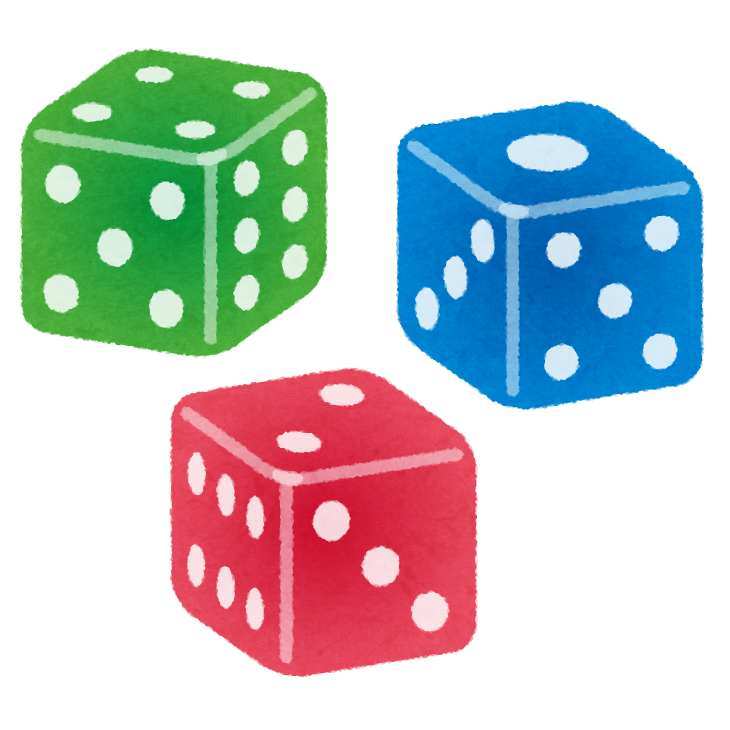
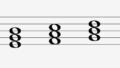

コメント