その9はこちら!
のりにぃ音楽理論 その9 セブンス、テンション、その他のコードを一気に学ぼう!
前回でコードはほぼ終わりましたが
まだ大切なスケールを解説していませんでしたね。
ロックのみならず、ジャズでも頻繁に使われるスケール!
ペンタトニックスケール
を覚えましょう!
クラシックでは
クラシックで僕は聞いたことがないですが
その理由も僕なりに書いてみますね。
ペンタトニックスケールってどんなスケール?
まずは言葉の意味から理解しよう!
「トニック」という単語は
今までコードでも何度も出てきていましたね。
音楽においては「主音」という意味でした。
では「ペンタ」という単語に意味があるはず!
uni「ユニ」は1でしたが、penta「ペンタ」は5という意味があります。
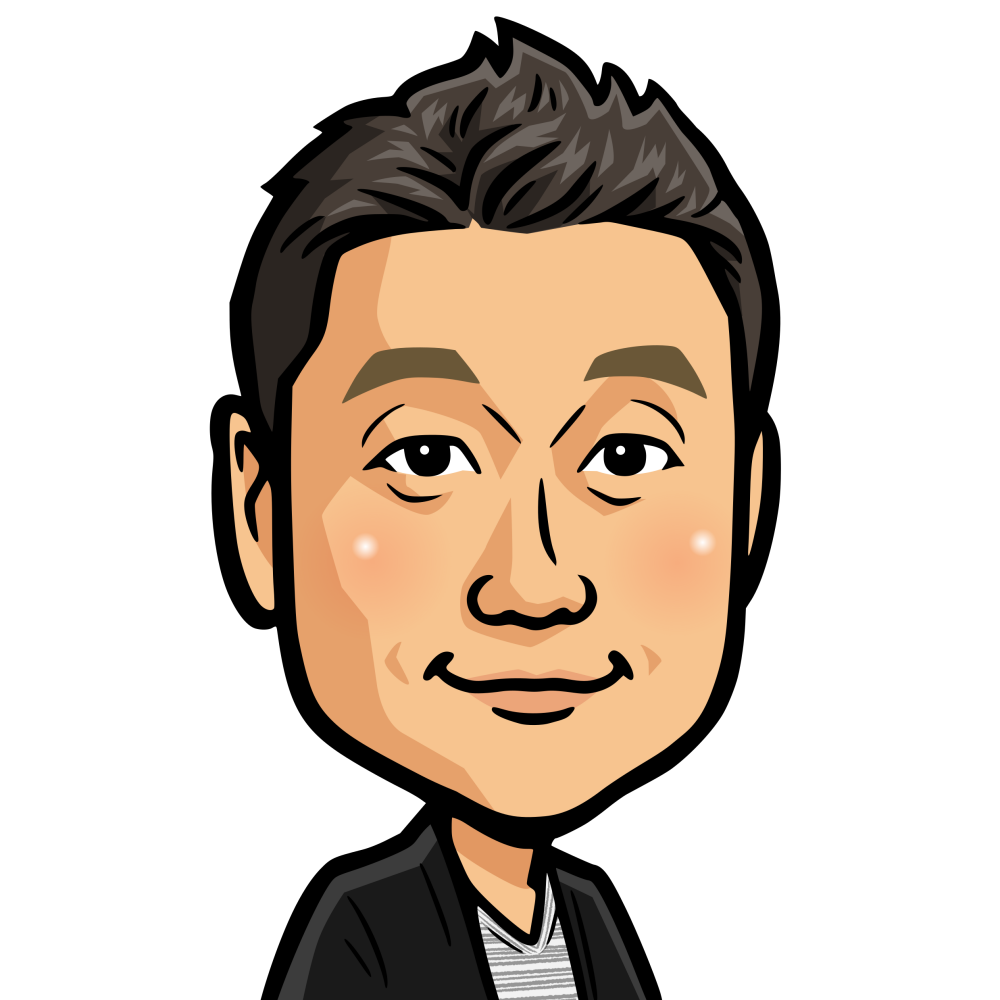
のりにぃ
同時多発テロで爆破されたのはペンタゴン(五角形)
つまり、ペンタトニックとは「5つの主音」という意味になります。
普通のスケールとどう違うのか
今まで見てきたメジャースケールとマイナースケールは
出てくる音は7つでしたね。
ペンタが5を表すのなら
音が2つ少ないことになります。
どの音が減るのかというと
4度と7度の音です。
メジャースケールの音から完全4度と長7度の音を省くと
ド レ ミ ソ ラ になります。
音を聴いてみよう
まずはペンタトニックの響きを聴いてみましょう!
オクターブ上のドも弾いています。
4度と7度を「抜いた」音階ということで
「よな抜き」音階と呼ばれることもあります。
なぜ4度と7度を抜くのか?
これは僕なりの解釈なのですが
今までの解説でも出てきた「半音の動き」ってありますよね。



コメント